本記事は、YouTubeチャンネル「あずみ in Germany」さんの動画「アジア人差別にブチギレた話 in ドイツ」をもとに執筆しています。
はじめに:動画をきっかけに考える“リアルな差別”
動画の中で彼女は、2021年からドイツで暮らす中で感じた「アジア人としての見られ方」や実際に遭遇した差別的な出来事を率直に語りました。
差別というテーマは非常にセンシティブで、一人ひとりが感じ方も受け止め方も異なります。
しかし、彼女の経験を通じて見えてくるのは、「異国で生きる」ということの現実と、それを前向きに受け止めようとする強さです。
第1章 差別体験 ― “ぶちギレた”瞬間とその背景
1-1. 久しぶりの「観光客」としてのドイツ
あずみさんは2021年からドイツに住み始め、大学生活を送りながら、現地の人々との交流も重ねてきました。
普段は学生が多い小さな街に暮らしており、日常の中ではほとんど差別を感じることがなかったといいます。
そんな彼女のもとに、日本から大学時代の友人2人が卒業旅行で遊びに来ました。
彼女たちは大学を卒業して社会人になる直前の年齢。
久しぶりの再会を喜びつつ、3人でドイツの都市部へ観光に出かけました。
ところが、電車の中や街中で感じた“周囲の視線”に違和感を覚えます。
「1人で歩いている時とは明らかに違う。アジア人3人というだけで注目されている感じがした」と語ります。
1-2. “アジア人女性は怒らない”という偏見
動画の中で印象的だったのは、「アジア人の女の子ってなめられやすい」という一言。
あずみさんによれば、ヨーロッパではアジア人女性に対して「おとなしい」「反論しない」「笑って流す」といったステレオタイプ(固定観念)が根強くあるとのこと。
そのため、見知らぬ男性から軽く冷やかされるような言葉をかけられたり、口笛を吹かれたりすることが珍しくありません。
しかし、同じ道をドイツ人の彼氏や友人と歩くと、そうしたことは一切起こらない。
つまり、“誰と一緒にいるか”“どんな見た目のグループか”によって、他人の態度が180度変わるのです。
それはまさに「アジア人女性」という属性だけで扱いが変わるという現実。
1-3. 電車の中で起きた言いがかり事件
そして今回、彼女が“ぶちギレた”のが、都市部の電車内で起きた出来事でした。
隣の座席にいた外国系の男性(ドイツ人ではない)が、突然あずみさんたちに話しかけ、こう言い放ったのです。
「ドイツにいるならドイツ語を話せ。母国語は家で話せ。」
しかもその男性のドイツ語自体も非常に拙く、ネイティブとは思えないレベルだったといいます。
つまり「外国人が外国人に向かって差別的な発言をした」構図でした。
あずみさんは落ち着いて返します。
「私もドイツ語は話せます。でも友達と日本語で話すのは自由です。」
しかし相手は聞く耳を持たず、彼女たちの日本語を真似してバカにするような仕草をし、「ドイツ語を話せ」と繰り返し叫び続けたとのこと。
最終的に彼女たちは別の車両へ移動。
ただその後も怒りが収まらず、「本当に腹が立った。何なんだこの人は、と思った」と振り返ります。
1-4. “怖かった”という友人、“むかついた”という本人
同行していた友人2人はドイツ語が分からず、「何を言われているか分からなくて怖かった」と話したそうです。
一方、あずみさん自身は怒りが先に立ちました。
相手の言葉を理解できるからこそ、理不尽さや不快さが強く胸に残ったのです。
「多分、酔ってたか薬をやってたのかもしれない。
正気じゃなかったとは思うけど、だからといって許せるわけじゃない。」
ドイツ語を学び、現地で生活基盤を築いている身として、
“外国人同士での差別”を目の当たりにしたことは大きなショックだったと語ります。
第2章 ドイツ社会のリアル ― 多文化共存の裏にある現実
2-1. 「差別はあるが、ドイツ人は基本的に優しい」
あずみさんは動画内で、「誤解してほしくないけど、ドイツ人は基本的に優しい」と繰り返しています。
大学では先生も学生もフレンドリーで、生活面でも助けてくれる人が多い。
カフェやスーパーなどでも外国人だからといって不当な扱いを受けたことはほとんどありません。
一方で、“外国人を下に見る一部の人”が確かに存在するのも事実。
特に都市部や観光地など、多国籍な人が行き交う場ほど
そのような態度を取る人に遭遇する確率が上がるといいます。
2-2. ヨーロッパは「多様性の実験場」
ヨーロッパは島国の日本とは違い、陸続きの大陸です。
国境を越えれば文化も言語も宗教も変わり、数時間の移動でまったく別の価値観の人々に出会います。
ドイツにはトルコ系移民、東欧系、アフリカ系、アジア系など多様なバックグラウンドを持つ人が共に暮らしています。
その結果、文化の違いが摩擦を生みやすい一方で、「共存する力」も強く育まれているのが特徴です。
彼女は「差別もまたヨーロッパの一部」と語ります。
「いろんな国の人が集まる以上、分かり合えないことがあるのは当然。 それも含めてヨーロッパなんだと思う。」
2-3. アジア人が感じる“見えない壁”
ヨーロッパでは黒人差別・宗教差別などがしばしばニュースになりますが、アジア人に対する差別は「小さく静かに」存在することが多いです。
例えば、
- レストランで後回しにされる
- 店員が冷たい態度を取る
- すれ違いざまに小馬鹿にしたような言葉を投げられる
といった“軽い無視”や“無意識の偏見”が、日常のあちこちに潜んでいます。
それは、言葉で明確に攻撃されるよりもむしろ心に残りやすい。
あずみさんのように長く住んでいる人ほど、その微妙な空気を敏感に感じ取るようになります。
2-4. “ぬるま湯ではない社会”の魅力
それでも彼女はドイツを愛しています。
その理由は、「この国には強く生きる人が多いから」。
日本では、空気を読み、波風を立てずに生きることが美徳とされがちです。
しかしドイツでは、個人の意見を持ち、理不尽に対してはきちんと声を上げる文化があります。
「みんな自分が自分がって感じだけど、それが逆にカッコいい。
ぬるま湯に浸かっていない、戦ってる感じがする。」
そう語る彼女の言葉には、
異国の厳しさを知りながらも、それを前向きに受け入れる強さがにじみます。
第3章 海外移住の心構え ― 差別とどう向き合うか
3-1. 「差別は人生の洗礼」という考え方
動画の最後であずみさんは、「差別くらい人生でされとかないと」と笑って語ります。
もちろん、差別を正当化する意味ではありません。
むしろ、実際に差別を経験したからこそ、「される側の気持ち」を深く理解できるようになったという意味です。
「むかつくけど、それも経験。差別されて初めて見える世界もある。」
このポジティブな視点が、彼女の生きる力の源になっています。
3-2. 留学・移住前に知っておきたい“現実”
これからドイツやヨーロッパに留学・移住を考えている人にとって、彼女の話は貴重な現実的アドバイスです。
- 差別は「ゼロではない」
- しかし「命の危険を感じるほどのものではない」
- ほとんどの人は親切で、困っていれば助けてくれる
つまり、構えすぎる必要はないけれど、“警戒心は持っておくべき”というのが実際のところです。
もし嫌な経験をしたとしても、それを「洗礼」と捉えて、自分の軸を保つこと。
それが、異国で長く生きていくためのコツなのだと感じます。
3-3. 差別を乗り越えて見えた“本当の多様性”
あずみさんは動画の最後にこう締めくくります。
「ヨーロッパでは差別もされるし、電車は遅れるし、みんな自分勝手。でも、それがここに生きるリアル。それを全部含めて私はこの国が好き。」
つまり、
「完璧ではない社会」を受け入れながら、その中で自分の居場所を見つける。
それこそが本当の意味での多様性です。
まとめ:異国で生きるという“強さ”
この動画を通じて伝わってくるのは、“差別を受けた”というエピソード以上に、
「それでも前に進む姿勢」です。
異国で生活するということは、言葉・文化・常識の違いの中で毎日小さな挑戦を繰り返すこと。
時に理不尽な出来事もある。
しかし、それを乗り越えた先には、自分の中に確かな「成長」と「誇り」が残るのです。
「むかつくこともあるけど、私はこの国で生きていく。」
そう語るあずみさんの言葉は、海外に憧れるすべての日本人へのエールでもあります。
終わりに
「アジア人としてドイツに住む」というテーマは、一見ネガティブに見えますが、実際には“世界の多様性を知る貴重な経験”でもあります。
差別を完全になくすことは難しい。
しかし、それをどう受け止め、どう行動するかは自分次第。
異国で生きるとは、他人の偏見に屈しない強さと、自分を信じる力を持つこと。
そして何より、「それでもこの国が好き」と言える心の広さが、海外で生きる人にとって最も大切な資質なのかもしれません。

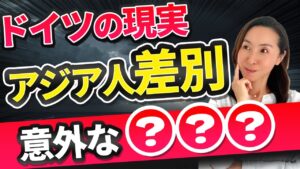
コメント