※この記事は、YouTube動画「ドイツで受けた差別、罵りのお話」をもとに執筆しています。
結論:差別は現実に存在する。それでも生き抜く強さが必要
ドイツは教育・福祉水準が高く、留学や移住先として人気の国です。
しかし、動画の語り手が体験したように、外国人、特にアジア人に対する差別は今も残っています。
外見や言葉の違いだけで、からかわれたり罵られたりすることがあるのです。
それでも彼はと語り、強いメンタルで前に進み続けています。
ドイツでの差別体験①:レバークーゼンで「ジャッキーチェン!」と叫ばれる
語り手が20歳の頃、ドイツ西部のレバークーゼンという町に住んでいた時のこと。
そこではアジア人が非常に少なく、街を歩くだけで強い視線を感じたそうです。
ある日、駅で電車を待っていると、ドイツ人の少年たち15人ほどのグループに囲まれ、「ジャッキーチェン!」と連呼されました。
彼らにとってアジア人=ジャッキーチェンという固定観念があり、それを面白がって叫んでいたのです。
最初は冗談のようでも、本人にとっては明確な人種的なからかい。
彼はその時、冷静に「僕はジャッキーチェンじゃないよ」と言い返し、その場を立ち去ったといいます。
この出来事は、ドイツの地方都市での「外国人への無意識な偏見」を象徴するエピソードです。
ドイツでの差別体験②:ケルンでの「モンチッチ」発言
次の出来事はケルン(Köln)でのこと。
サッカークラブ「FCケルン」の試合を観戦した後、街を歩いていたときに見知らぬドイツ人男性に声をかけられました。
「お前、モンチッチみたいだな!」
モンチッチとは日本発のぬいぐるみ人形で、1970年代にヨーロッパでも流行しました。
当時を知る年配のドイツ人にとっては懐かしい存在ですが、それを「アジア人=モンチッチ」という見た目のからかいとして使うのは失礼なことです。
語り手は「ありがとう」と軽く流したものの、内心では強い違和感を覚えたと語っています。
一見冗談のようで、実は外見への偏見が根底にある
こうした「無意識の差別」こそが日常的に最も多いのです。
ドイツでの差別体験③:コロナ禍での「お前らのせいで!」という罵声
最もつらかったのは、コロナウイルスが流行していた時期のこと。
アジアから感染が広がったという報道の影響で、ドイツ国内ではアジア人に対する偏見が一気に強まりました。
彼が街を歩いていると、後ろから突然
「お前らのせいでコロナが始まったんだ!」
と叫ばれたといいます。
マスクをして歩いても、しなくても、ただ「アジア人」というだけで攻撃される。
このような状況が各地で起こっていたのです。
ドイツでは2020年当時、アジア系住民への嫌がらせが急増し、「Stop Asian Hate(アジア人差別をやめよう)」という運動がSNSで広まりました。
それだけ深刻な社会問題だったのです。
差別を受けても「気にしない」強さ
動画の語り手は、こうした経験をしてもなお、「僕は気にしない」と語ります。
しかしその裏には、長年積み重ねてきた「慣れ」と「覚悟」があります。
彼は学生時代から先生に嫌味を言われたり、「テストの点だけ良いアジア人」として扱われたりしてきたそうです。
それでも、「生きているだけでおられる」「笑い飛ばせるようになった」と言います。
怒りや悲しみを超えた先に、精神的な強さがあるのです。
背景:なぜドイツでアジア人差別が起きるのか?
ドイツはEU内でも外国人比率が高い国の一つで、特にトルコ系・シリア系・東欧系の移民が多い国です。
しかしアジア系人口は比較的少なく、地方では「珍しい存在」になりがちです。
また、戦後の単一民族的な価値観が今も残っており、「外見が違う=よそ者」という意識が根強い地域もあります。
さらに2020年前後のコロナ報道では、「中国発のウイルス」という偏った報道が多く、アジア全体に対する差別感情を助長したとも言われています。
こうした社会構造とメディアの影響が、彼のような留学生を苦しめる要因になっているのです。
それでもドイツに住む理由:得られる経験と視野の広がり
差別の現実がある一方で、ドイツ生活には多くの学びもあります。
異文化の中で自分をどう表現するか、困難な環境でどうメンタルを保つか——それらは日本では得られない経験です。
語り手は「これも人生の一部」「笑って話せるようになった」と振り返っています。
辛い体験を通して、人としての強さと多様性への理解が深まったといいます。
まとめ:他人の無理解に負けない心を持とう
この動画が伝えているのは「差別の実態」だけではありません。
それ以上に、「それでも生きていく強さ」の大切さです。
ドイツで叫ばれた「ジャッキーチェン」「モンチッチ」「お前らのせいで」——
これらの言葉は確かに心を傷つけます。
しかし、彼はそれを笑い話に変え、自分の成長へとつなげました。
私たちも海外で同じような体験をしたとき、
「自分の存在を誇りに思う心」を忘れずにいたいものです。
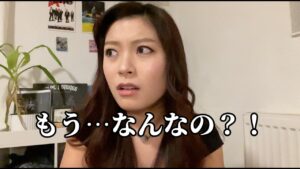
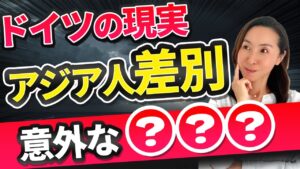
コメント